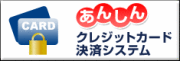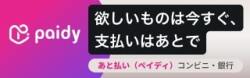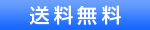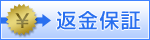親鸞聖人の生涯
「京都。日野に誕生、九歳の春に出家」
親鸞聖人が誕生された平安末期は、戦乱、天災が続き、世はまさに末法の様相を呈し、民衆は時代の荒波に翻弄されていました。
記録によると、親鸞聖人は四歳で父を亡くし、八歳で母を亡くした、といわれます。
誕生地は京都郊外の日野。
父は藤原氏の流れをくむ日野有範。
幼名は松若丸。
九歳の時慈円僧上のもとで得度。
場所は青蓮院の白川房。
京は春だったが、時代は戦乱のさ中でした。
「比叡山に登る。修行は二十年に及んだ」
出家した親鸞聖人は、比叡山に登り修行。
比叡山は当時の日本仏教の最高学府でした。
後の鎌倉仏教の祖師となる道元や日蓮も、みな比叡山で修行しています。
親鸞聖人の修行の場は比叡山の横川、常行三昧堂です。
常行三昧とは、堂内の阿弥陀如来をまわりながら、阿弥陀如来の名を九十日間にわたって念じ続ける行のことをいいます。
このような厳しい修行とともに、修学にひたすら励みました。
一心不乱の研鑚にもかかわらず親鸞聖人の心は満たされませんでした。
そして山を降りることを決意。
上山以来二十年を経過していました。
時に親鸞聖人二十九歳。
「聖徳太子の夢告を得、法然上人の元へ」
比叡山を降りた親鸞聖人は、聖徳太子ゆかりの寺、京都の六角堂に向かいました。
そして、この寺で百日間の参籠に入りました。
九十五日目の暁、聖徳太子の夢告を受けました。
聖徳太子の偈を受けた聖人は、法然上人のもとに参ることを決意。
法然上人が居る、東山吉水に走りました。
法然上人は専修念仏の教えを説き、多くの人が集まっていました。
法然上人は念仏往生においては、制約するものは何もない、と説いていたからです。
法然上人の弟子となった親鸞聖人は、師を仰ぎ研鑚を重ねました。
一心に阿弥陀仏の名を称える念仏の教えは、男女や身分に関係なく広がっていきました。
しかし、そのことは旧仏教の批判を受けることになり、ついに念仏禁止令が出されました。
「念仏者の弾圧。越後へ配流される」
念仏者が弾圧されたこの事件を承元の法難と呼びます。
事件には様々な要因がありました。
二人が斬首、八人が流罪となったのです。
法然上人は四国へ。名は藤井元彦とされた。
親鸞聖人は越後へ、名は藤井善信とされた。
この時、法然上人七十五歳、親鸞聖人三十五歳、再びこの世でまみえることのない永遠の別れでありました。
後に聖人はこの時の心境を、(しかればすでに僧にあらず俗にあらず、このゆえに禿の字をもって性とす)と述懐しておられます。
いわゆる(非僧非俗)の宣言です。
「恵信尼との出会い。愚禿親鸞と名のる」
親鸞聖人の配流先は越後、現在の上越市。
上陸したのは居多ヶ浜の海岸。
そこから五智国分寺に至りました。
現在、この地は親鸞聖人の旧跡となっています。
念仏の教えを聞くゆとりもない人々、厳しい環境。
その中でも聖人は教えを広めていかれました。
やがて、聖人は、一人の女性と出会います。
後に聖人の妻となる恵信尼です。
流罪の日々、ひたすら苦難に耐え、子供も生まれました。
親鸞聖人は、流罪の地越後で、自らを愚禿親鸞と名のりました。
ちなみに禿とは、髪を切りそろえた状態をいいます。
僧でもなく、俗人でもない身、禿とは非僧非俗の象徴なのです。
「関東への旅立ち。稲田に草庵を結ぶ」
建暦元年、親鸞聖人は流罪をとかれました。
三十九歳になっていました。
しかし聖人は、すぐに京には帰らず越後にとどまりました。
やがて聖人は妻恵信尼と信蓮房を伴い東国(関東)へ向けて旅立ちました。
行先は常陸国。
一方京都に戻った法然上人は翌年はじめに往生をとげておられます。
関東に入った聖人は当初下妻に草庵を、後に稲田に草庵を結びました。
稲田は現在の茨城県笠間市。
現在西念寺が建っています。
以来二十年間、常陸を中心に念仏の教えを説き続け、多くの念仏者が生まれました。
聖人の主著(教行信証)の草稿を執筆したのもこの地です。
「念仏、ひと筋、偉大な生涯をとじる。往生は九十歳」
親鸞聖人は六十二歳になっていた。妻・恵信尼も越後に帰ることになりました。
聖人は京に帰ることを決意。
教行信証の完成を急ぐため、といわれています。
京においても様々な困難がありました。
しかし聖人の信念のゆらぐことは、いささかもありませんでした。
そして弘長二年十一月二十八日覚信尼らの見守るなかで九十年の偉大な生涯を終えられました。
往生を間近にした聖人は、ひたすらに念仏を称えていたということです。
「浄土真宗 真宗を知る 辞典」より