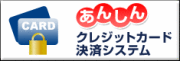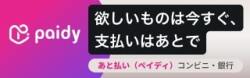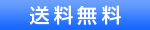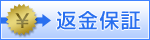蓮如上人の生涯
戦乱と飢饉の世、真宗の教えを広めた中興の祖
「貧しかった幼少時代を耐え本願寺八世に」
蓮如上人が誕生されたのは、応永二十二年。
室町時代にあたります。
親鸞聖人の末裔です。
生母は上人六歳の時、本願寺を出ていかれました。
当時、本願寺は寂れ貧しさの極みにありました。
蓮如上人は長男であったが、生母が去ったあとは部屋住みという立場におかれ、世の辛酸をなめることになります。
このような上人の生活は四十二歳までつづきます。
しかし、時代は蓮如上人を求めていたのでしょうか、蓮如上人は本願寺第八世となります。
ここから一代で本願寺を復興させた上人の激動の生涯が始まります。
「民衆の心を掴み教勢を拡大するも、厳しい弾圧に遭う」
本願寺の住職となった蓮如上人は様々な改革に着手します。
近江・畿内・東海と布教の旅を精力的に行ないました。
次第に教勢も拡大、戦国乱世の世、よるべを失いつつあった民衆の心を確実に掴み、門徒の数も急速に増加していきました。
しかし、教勢の拡大は、やがて他の教団の反発を受けるようになっていきました。
そして、寛正六年比叡山宗徒の襲撃に遭い本願寺は破却しました。
蓮如上人と行動を共にする門徒は防戦したが、かないませんでした。
これを寛正の法難と呼びます。
「布教の旅へ、本拠地の吉崎御坊は隆盛を極めた」
本願寺をさった蓮如上人は各地を転々とします。
それは布教の旅でもありました。
大津の三井寺に親鸞聖人の御影像を建てたのは文明元年。
時に蓮如上人五十五歳。
やがて上人は北陸へ向かわれました。
越前(福井県)の吉崎、蓮如上人は、ここに本拠地を移し、以降四年間、ここに滞在します。
吉崎の地形は天然の要塞となっており、上人はここに坊舎を建てた、これが吉崎御坊です。
吉崎御坊は北陸布教の拠点となりました。
上人の吉崎での活躍はめざましく「お文=御文章」や「六字名号」など多数書きのこされました。
この文書伝道は真宗復興の原動力になった、とされています。
「吉崎を去り、悲願の本願寺再興にのり出す」
しかし、教勢の拡大は時の権力との摩擦を生み、各地で一向一揆が勃発、上人は四年余り滞在した吉崎を去ることを決意。
各地を転々と教化して歩くことになります。
文明十年、念願の本願寺再興にのり出します。
本願寺破却から十三年、上人の悲願でした。
七十六歳で引退後も石山(大阪)御坊を建立。
明応八年波乱に富んだ八十五歳の生涯をとじられました。
「浄土真宗 真宗を知る 辞典」より